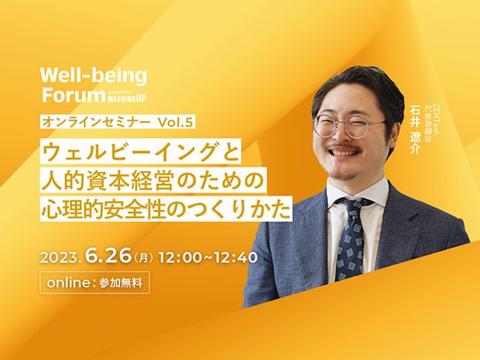| CARVIEW |

画像/MASHING UP
多様性のあるイノベーティブな環境をつくっている企業は、女性の健康に向き合い始めている。とはいえ、長く女性の「自己責任」とされてきた課題に、組織としてどのようにサポートしていくべきなのかわからず、困惑する声もあるのは当然だろう。そんなときに参考にしたいのは、先行している企業の声だ。
2022年11月に開催された「MASHING UP CONFERENCE vol.6」では、「働く体をサポートする組織・社会をどうつくる?」と題したトークセッションを開催し、ヤフー グッドコンディション推進室の鈴木麻未さん、オイテル専務取締役COOの飯﨑俊彦さんが登壇。フェムテック関連事業を展開するfermata(フェルマータ)の中村寛子さんがモデレーターを務め、それぞれの事例を紹介しつつ、これからの組織・社会にあるべきサポートについて語り合った。
PMS症状や“更年期ロス”に昇進が阻まれる

fermataの中村寛子さん。生理や更年期による経済損失についてのデータを示した。
撮影/伊藤圭
女性の健康について考えるときに、まず必要なのはそこにどのような課題があるのか、共通認識を持つことだ。そこで中村さんから、さまざまな研究データから前提となるファクトが紹介された。
「生理前のPMS症状を理由に、昇進辞退を経験または検討する女性は2人に1人(※1)。生理によって不調を感じている日数は、年間60日あるとされています。その結果、月経随伴性による労働損失は年間約5000億生まれているのです(※2)」(中村さん)
さらに、近年では女性の健康の問題として頻繁に取り上げられるようになってきた生理の話とは違い、未だにタブー視されている更年期の問題もある。
「管理職に多い40代半ば~50代半ばは、ちょうど更年期の時期と被るんですよね。その時期に、更年期症状を経験している人は約4割。更年期症状を理由に昇進辞退を検討、経験する人が4割(※3)。更年期離職による経済損失は約4200億といわれています(※4)。これを示す“更年期ロス”という言葉も生まれているのです」(中村さん)
※1、※3 大塚製薬「女性の健康と仕事への影響に関する調査」(2021年9月実施)より。
※2 経産省ヘルスケア産業課「健康経営における女性の健康の取り組みについて」(2019年)より。
※4 NHK みんなでプラス「“更年期ロス” 100万人の衝撃 離職による経済損失 年間6300億」より。
Advertisement
女性の健康だけをサポートするのは不平等?

ヤフー グッドコンディション推進室の鈴木麻未さん。「男女ではなく、課題があるところにサポートをしていきたい」と語る。
撮影/伊藤圭
ヤフーでは、「情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。」ということをミッションとして掲げている。これを実現するために、「働く人とその家族の心身の健康が第一条件。そして、多様なお客様のニーズに応えるためにも、社内の多様性を重視しています」と鈴木さんは言う。
「そのために、不妊治療休職制度などのさまざまな制度を整備すること。それに加え、女性だけでなく男性社員も巻き込んだ、文化を醸成するための取り組みを進めています」(鈴木さん)
女性の健康を取り上げることでよくある障壁の一つが、「女性の健康だけをサポートするのは不平等ではないか?」というものだ。これに対して鈴木さんは、こう指摘する。
「たとえばメタボや喫煙者に対する支援を受けているのは男性のほうが多いですが、それをおかしいという人はいないのです。男女ではなく、課題があるところに適切なサポートをしていこうという、それによってどのくらい救われる人がいるのかと考えることで、多くの方が納得できるようになるのではないでしょうか」(鈴木さん)
女性は約40年間、生理用品を買い続けている

オイテル専務取締役COOの飯﨑俊彦さん。女性トイレにナプキンを常備し提供するサービスは、様々な施設や企業で導入されている。
撮影/伊藤圭
オイテルでは商業施設やオフィス、学校施設などの女性用トイレの個室にナプキンを常備して提供するサービスを展開。全国173か所で導入され、企業の福利厚生としても取り入れられている。
「きっかけは、ネット上でのある女性の『トイレットペーパーは常備されているのに、なぜ生理用品はないのですか』という声でした。たしかに、女性は初潮を迎えてから約40年間、生理用品を購入することを強いられているのです」(飯﨑さん)
オイテルのシステムでは、生理用品のディスペンサーにデジタルサイネージを搭載させ、広告費で無料の生理用品がまかなえる。福利厚生として取り入れた企業からは「今まで導入した福利厚生の中で一番社員から喜ばれた」という声もあるという。
女性の「当たり前」に問いかける
女性特有の健康問題に対して、「生理や更年期は本人が対処して当たり前、生理用品は自分で買うのが当たり前という風潮だったのに対して、そうではないのではないかと問題提起することが重要だということがわかりました」と中村さん。
セッションでは参加者同士のワークショップも開催。「生理についてオープンに話すか話さないかも、個の自由」という意見も出された。まずは個人の自由を尊重した上で、先行する企業の取り組みも参考にしながら、着実に議論を進めていくべきだろう。

撮影/伊藤圭
MASHING UP CONFERENCE vol.6
働く体をサポートする組織・社会をどうつくる?
飯﨑 俊彦(オイテル 専務取締役COO)、鈴木 麻未(ヤフー グッドコンディション推進室)、中村寛子(fermata)

![]() イベント
イベント
JOIN US
MASHING UP会員になると
Mail Magazine
新着記事をお届けするほか、
会員限定のイベント割引チケットのご案内も。
会員限定コンテンツ
DEI、ESGの動向をキャッチアップできるオリジナル動画コンテンツ、
オンラインサロン・セミナーなど、様々な学びの場を提供します。

.png)